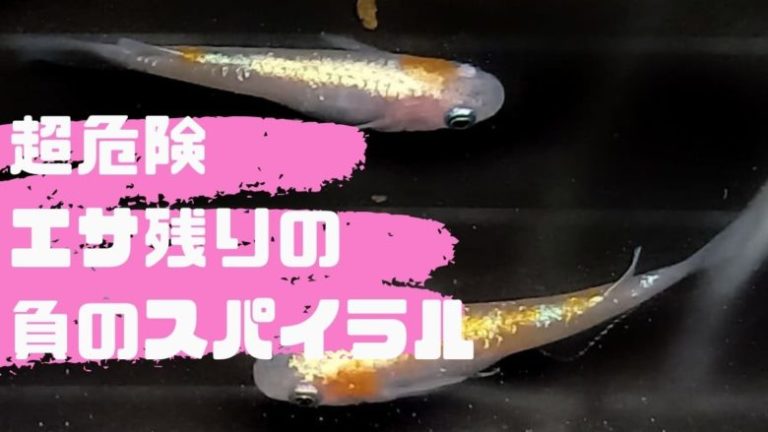最近まで調子が良かったメダカたちが、突然調子を崩して「ポツポツ死」が止まらず慌ててしまった経験はありませんか?

私は、こういう経験が意外に多くて、何度も悔しい思いをしてきました。

「絶好調」から「ポツポツ死」への落差が大きくて、とても悲しい気持ちになりますよね・・・

経験上ですが、このようなケースは、知らず知らずに餌が過剰になっていることが多いんです。
最近まで、元気に餌を食べていたメダカたちが、突然食欲を失って水槽の底に潜り「ポツポツ」と死にはじめて、慌てた経験はありませんか?
私は、このような経験が多くて、ずっと悩み続けてきました。
みなさまも、私と同じような経験をして、悲しい思いをしていませんか?
このような中、私が最近辿り着いた原因が 、メダカの体調変化に気が付かないまま、餌が過剰になってしまい水質悪化が加速する現象です。

私は、これを「餌残りの負のスパイラル」と呼んでいます。
今回は、なぜ気が付かないうちに餌の食べ残しが増えてしまうのか、そして食べ残しがどれほど危険なのかについて解説をさせていただきます。
食べ残しの餌からの水質悪化の連鎖「餌残りの負のスパイラル」とは

まず、最初に見ていただきたいのが以下の動画です。
私が飼育している「マリアージュ」の動画です。
メダカが本当に元気だと、これくらい俊敏に泳ぎ続けます。
飼育中のメダカが、この動画に比べて泳ぎが緩慢だったり、泳いだり止まったりを繰り返えす場合や底に潜ってばかりの場合は、飼育水が汚れていることが予想されます。

発見が遅かった場合は、既に病気に罹患している可能性もあります。
汚染が早い段階でしたら、水換えだけで元気を取り戻します。
でも、メダカが水底に潜りっぱなしになるまで状態が悪化していると、水換えだけでは回復が難しいかもしれません。
一時的に元気に戻ったように見えても、長生きはできないかもしれません。
過剰な餌による餌残りの危険性
①メダカの調子がいいので、たくさん餌を与えている。
②飼育水が汚れてくると、メダカの食欲が低下する
③(食欲の低下が原因となって)餌の食べ残しが始まる
④食べ残した餌が原因で、飼育水の汚染が加速する。
⑤メダカの食欲不振が進み、更に餌の食べ残しが増える
⇒飼育者がそれに気が付かないで食べ残しが増加
⑥ ④⑤の繰り返しで急速に水の汚染が進む
⑥急に餌食いが悪くなったように感じ、メダカの体調不良に気が付くが、既に手遅れ寸前の状況
⑦「ポツポツ死」が止まらなくなる

この「負のスパイラル」の恐ろしいところは、数日前まで元気で餌食いが良かったメダカたちが、たった数日で弱ってしまうことです。
なぜ?餌の食べ残しが増えると「餌残りの負のスパイラル」が起きてしまうのか?

調子が良い水槽ほどメダカにたくさんの餌をあげたくなり、ろ過バクテリアの減少を気にして、水換えを控えがちではありませんか?

そこに落とし穴があるのです。
理由は単純です。
元気で餌食いが良い水槽へは、ついつい餌をたくさんあげたくなりますよね?
そして、気持ちの面で、この水槽は調子がいいから安心だ。
きっとバクテリアもしっかりわいている。
バクテリアを減らさないために、水換えは控えたほうがいい。
そう考えがちではありませんか?

飼育経験が長くなるほど、そう判断しがちではありませんか?
そこが「餌残りの負のスパイラル」の怖さです。
餌をたくさんあげたい気持ちと、水換えを躊躇する気持ちが渦を作って循環し始めると、元気なメダカが数日で弱って死んでしまうリスクが高まります。
食べ残しの「負のスパイラル」を避けるために意識すべき事と回復方法

ベテランのブリーダーさんは、みなさん口を揃えて「餌は少量を数多く与えると良い」と仰います。

本当にこれに尽きると思います。

そして、大切なのは「少量」の餌の考え方です。
少量の餌の考え方とダメージの回復方法について
よく観賞魚の飼育の本を見ていると「餌は5分以内に完食できる量を与えることが基本」と書いていることが多いですよね。
私も、飼育をはじめてしばらくは、それをしっかり守って飼育してきました。
でも、経験を積んでいく中で、その給餌方法に疑問を持つようになり、今では与えた瞬間に食べ尽くす量しか与えてません。
与えてから1分ほど経過しても浮いていたり、食べ残されて水槽の底に沈んでいるような餌は、その場でスポイトで回収してください。

弱くて餌の取り合いに負けるような個体は、別水槽で育ててあげてください。
弱い個体に餌が回るようにと餌が過剰になるのは危険です。
日々の観察と早めの水換えが大切
大切なことは、餌を与える1分間しっかりメダカの泳ぎや食べっぷりを観察することです。
そして、泳ぎが遅い、餌食いが悪いと感じたら、すぐに1/3程度の換水を実行してください。
たとえ、週1とか週2のルーティンで水換えを実施していたとしてもです。
そして、その日は水質維持のために餌も切る方が安心です。
躊躇している間に「ポツポツ死」は加速します
「餌残りの負のスパイラル」に陥った水槽は、アンモニアなど有害物質の浄化が追いついていません。

躊躇している間に、メダカが衰弱してポツポツと死んでしまいますよ。
たとえ換水後に数匹のメダカが死んでしまっても、水槽全体のメダカが元気になるまで、心を折ることなく毎日1/3の換水を続けてください。
※交換する水の温度やpHのショックをちゃんと気にしていることが大切です。
私は、水換えで死んでしまうメダカがいても、衰弱の程度が酷かったのだと考えるようにしています。
そうやって心を強く持たないと、迷いと不安で水換えを継続できなくなり、結果全滅を回避できなくなることが多いです。

明確に説明はできませんが、同じ水槽のメダカでも水質悪化で受けたダメージに強弱があります。
私の経験上ですが、水換え直後に少しも回復した様子を見せないメダカは、餌を食べたり泳いでいたとしても、既に致命傷を受けていると思われます。
その致命傷を受けているメダカの死を、水換えのショックが原因だと思い込むと、迷いで水換えを継続できなくなるので注意が必要です。
これを守ることで、ほとんどのケースは冒頭の動画のような元気な泳ぎを取り戻します。

下の記事に詳しく「ポツポツ死」についてまとめています。
必ず守って欲しいこと

冒頭でも書きましたが、水の良し悪しを感覚だけで判断しないでください。
見えない場所でジワジワと着実に進行するのが水質悪化で、メダカが元気な時ほど水質悪化の罠が潜んでいるとご理解ください。
水質調査のプロでも、検査は検査薬や検査機器で判断していて、経験だけで判断していないとお聞きしました。

私は、大切なメダカを失う前に、アンモニア検査薬の導入をおススメします!

手を尽くしてもメダカが元気にならない場合
換水を継続しても元気にならない場合は、既に致命傷を受けていると思います。
私の経験では、致命傷を負ったメダカを「薬浴」「塩浴」しても、水質変化に耐えられずに死んでしまうことが多いです。
ですから、一定期間水換えをしても回復しない場合は、奇跡を信じて「薬浴」などをせず、濃いグリーンウォーターの中で回復を祈ることにしています。
グリーンウォーターを使うのは、弱っているメダカに粉の餌を与えても、再度「餌残りの負のスパイラル」を起こしてしまうリスクがあるからです。

私のところでは、これは致命傷かなと思っても、半数くらいグリーンウォーターの中で回復してくれています。
それでも、産卵が止まったり、長くは生きられなかったり、ある意味で後遺症を受けていることが多く、こうならないために早期発見を心掛けて下さい。
室内での加温飼育の難しさ
室内での加温飼育は本当に難しいです。
加温すると水が傷みやすく、アンモニアの毒性が上がりやすいことが理由の一つです。
(参考)アンモニアの害についての記事
(参考)活き餌を使うと餌の管理がグッと楽になります

基本的な餌の回数と量についての記事です。

実際の飼育場の様子です。

言葉だけでは伝わらない雰囲気を、ご確認いただけると思います。
最後に
ここまで餌の与えすぎと「ポツポツ死」の関連性についてご説明してきました。
餌を与えて、それをメダカが食べる日常の中に、見えない水質悪化のリスクが潜んでいます。
「ポツポツ死」を防ぐために、調子が良い水槽ほど、意識して観察の目を強めてください。
この記事がみなさまのお役に立てると嬉しいです。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました。