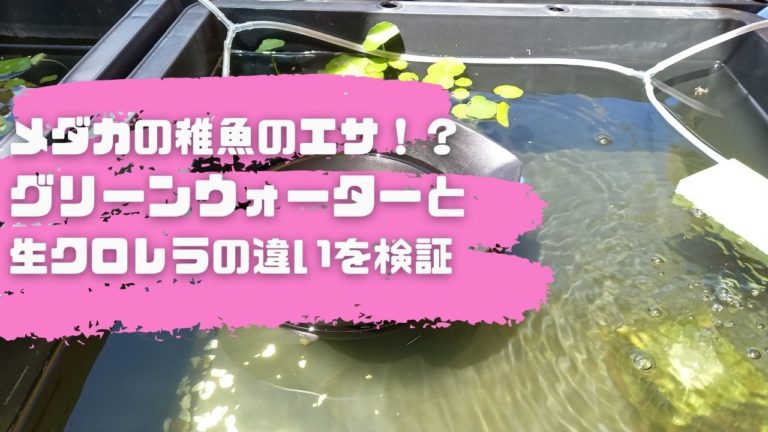みなさまは、秋から春先までどのようにしてグリーンウォーターを確保していますか?

室内で繁殖をされる場合でも、グリーンウォーターがあるだけで稚魚の生き残りが随分違うと思います。

でも、冬の期間にグリーンウォーター手に入れるのって難しいですよね。

私は、照明や温度をアレコレ弄って、室内でグリーンウォーターを作ることにチャレンジした時期もありました。

でも今は、割と生クロレラを代替品として使用しています。

ところで、生クロレラってグリーンウォータの代替品になり得るのでしょうか?

今回は生クロレラのメリット・デメリットについて解説をさせていただきます。
秋から早春にかけての気温が低く太陽光が弱くなる時期は、どうしてもグリーンウォーターを維持することが難しくなりますよね。
グリーンウォーターでの飼育は、色揚げなど様々なメリットがあるので、できれば年間を通してグリーンウォータを入手したいのが本音。
それに、グリーンウォーターが手に入らないと、ミジンコが培養できないし、稚魚の歩留まりも落ちてしまって大変ですよね。
そこで、グリーンウォーターの代替品として登場するのが市販の「生クロレラ」です。
市販の「生クロレラ」は、値段もソコソコしますし、使用についても賛否両論あって導入を迷っている方も多いのではないでしょうか?
今回は、「グリーンウォーター」と「生クロレラ」のメリット・デメリットについて検証ていきたいと思います。
簡単なグリーンウォーターの培養方法ついて


ここから、具体的なグリーンウォーターの培養について解説していきます。
メダカ飼育におけるグリーンウォーターの特徴とそのメリット


グリーンウォーターは、メダカの飼育水が自然に緑色に変化した状態を指す言葉で、水中に大量の植物プランクトンが発生しているので緑色に見えます。
メダカの糞や食べ残しなどの有機物が増えると、有機物が分解されて有毒なアンモニアに変質します。
これが、メダカが衰弱してしまう原因になります。
ところが、グリーンウォーターで飼育していると、植物プランクトン不要な成分を栄養として吸収するので、水を浄化する効果が期待できます。
また、植物プランクトンが直接メダカの餌になるだけでなく、ゾウリムシやミジンコの餌にもなり、自然に水槽内に食物連鎖が産まれることもメリットです。

メダカにとってグリーンウォーターは、食料であり、浄水場であり、養殖場なのです。
また、植物プランクトンは文字通り植物ですので、光合成によって水中の二酸化炭素を酸素に置き換える効果があります。
まさにグリーンウォーターは、メダカ飼育において万能選手なんです。
※植物は光合成で二酸化炭素を酸素に交換しますが、夜間は酸素を消費するので、多すぎる水草や濃すぎるグリーンウォーターは酸欠の原因になることがあります。
ご注意ください。
グリーンウォーターと雨の関係とその危険性

グリーンウォーターで飼育している水槽に、大量の雨が降り込むと、緑色がさめて水が澄んでしまうことがあります。
この状態をよく観察すると、水が澄むだけではなく、底に濃い緑色の堆積物が発生していることに気が付くと思います。
これは、植物プランクトンの死骸で、そのまま放置すると腐って有害になりますので、水換えも兼ねて、一緒に吸い出してください。
植物プランクトンの死滅を防ぐためには、波板などを利用してメダカの水槽に雨が降り込まないようにする工夫が必要です。
メダカにとって雨は、急激に水温を下げて、水質を酸性にし、グリーンウォーターをダメにしてしまう、謂わば天敵なんです。



最終的に私は屋根を作りましたがお、金をかけて対策をするくらい雨は怖いですよ・・・

グリーンウォーターと危険なアオコとの混同に注意が必要

アオコとは、水面に浮遊性藍藻が大量繁殖している状態です。
アオコは、その見た目がグリーンウォーターに似ていることが問題です。
アオコはメダカやエビに有害な毒素を出す上、水面を覆って植物プランクトンの光合成を妨げる悪者ですが、グリーンウォーターに似てるので気が付きにくいんです。
参考ですが、グリーンウォーターとアオコの一番の違いは悪臭です。
基本的にグリーンウォーターは臭いませんが、アオコは強い刺激臭があります。
もし強い臭いを感じたらアオコの可能性があります。
できるだけ速やかに水槽をリセットしてください。
その他グリーンウォーターの使用する場合の注意点
グリーンウォーターのデメリットの1点目は、飼育水が緑色に濁るため、水槽内の観察が難しくなり、ヤゴなどの捕食者を見落としたり、糞や食べ残しの発見が困難になることです。
2点目は、メリットで光合成を上げましたが、実は日が沈むと植物は酸素を消費します。
そのため、グリーンウォーターが濃い=植物プランクが多すぎると、逆に夜間の酸欠の原因になってしまいます。
ハイポネックス(液体肥料)を活用したグリーンウォーターの作り方

グリーンウォーターの作り方は、以下の記事をご参照ください。
ただ、夏場であれば、太陽の下に飼育水を数日放置するだけで、グリーンウォーターはしっかり仕上がりますのでご安心ください。

生クロレラの特徴と使い方ついて
クロレラは、とても微細な単細胞緑藻で、川や沼などに生息しており、大昔から存在する植物です。
このクロレラを(商品によりますが)生きた状態で販売しているのが生クロレラです。
市販されている生クロレラの濃縮原液は臭いがとても強く、最初は「腐ってる!?」と疑問を持つこともありますが正常です。
また、常温ではすぐに傷むうえ、冷蔵で長くて1カ月、冷凍でも傷んでしまう扱い難さを持っています。
そのため、使用するためには必要な分量を定期的に購入する必要があります。
生クロレラの賛否について
生クロレラを直接メダカの飼育水槽に入れると、すぐに成分が沈殿し、逆に飼育水を汚してしまうので、ミジンコの餌としてしか使用しないという意見も少なくありません。
私もその認識を持っています。

基本的に生クロレラをメダカに直接添加するのは避けた方が賢明です。

どうしてもグリーンウォーターの代替えに使う時は、ごく少量に留めてください。
稚魚(針子)飼育にに生クロレラはあり?なし?

メダカは一般に、約3か月で大人になると言われています。
ですが、繁殖家レベルの方は僅か1か月~1カ月半で産卵を始めるまでに大きく成長させることができます。
めだか屋SUNでも、時期による影響はありますが、孵化から1カ月半あれば若魚サイズまでは成長しています。
まだ未検証ですが、産まれて最初の2週の間に、どれだけ豊富に栄養を取れたかで、その後の成長が違ってくると言われています。

確かに、栄養価が高いブラインシュリンプを与えると、成長スピードがグンと上がります。
稚魚の死因No.1が餓死であるとも言われていますし、それだけメダカにとって稚魚時代の食事は大切です。
メダカは胃袋を持たない生物なので、人間のように食い貯めができません。
メダカは今必要な栄養分しかお腹に蓄えられないので、1日分の栄養を摂取するためには、ずっと泳ぎ食べ続けないと、栄養失調になってしまうのです。
特に、メダカの稚魚は体が小さいので、全くと言っていいほど食い溜めができません。
そのため、大人のメダカの感覚で餌をあげても、その殆どが食べ残され、水槽の底に沈んでいきます。
そして、その餌が腐って飼育水を汚すので、水が汚れ、更に食欲が低下する、食べ残しの悪循環が始まります。

餌を食べ残して水が汚れて、食欲不振で食べ残しが増える。

これがメダカ飼育における究極の悪循環です。

私の飼育場の動画ですが、生クロレラを使ってミジンコと共生飼育している、メダカの幼魚の様子が収録されています。
餌の食べ残しの悪循環を防ぐためには、少ない量を1日に何回も与える必要があります。

一般の愛好家の方は、仕事や家事があり、終日メダカの餌やりに没頭することは不可能ですよね。
そのため、ゾウリムシやミジンコといった活き餌を、いつでも食べられるように与えるのですが生クロレラはそれらの活き餌の餌としても最強なのです。

前述しましたが、メダカに「生クロレラ」を直接与えることについては賛否があります。

というより、私の肌感覚では否定派が多いと思います。
私も、生クロレラのを直接与えるのは微妙なので、飼育水に10,000倍程度まで薄めて稚魚に与えています。
そして、その中でミジンコも同時に増やしています。(というより、活き餌として与えたミジンコが勝手にクロレラを食べて繁殖しています。)
そうすることで、生クロレラを稚魚とミジンコが消費し、底に沈殿する生クロレラを限りなく少なくできています。
また3日に1回は1/3以上換水しているので、目立って水質が悪化することもありません。
このあたりが、換水による水質ショックや水流で背が曲がるリスクと水質悪化のトレードオフになるため、クロレラ否定派のご意見につながるのかなと考えています。
小さな稚魚のうちは、換水を最低限に抑えたいのは共通だと思います。

私は水質ショックを最小限にするため注水は点滴容器で行っています。

こちらが、私が手作りした点滴容器です。

一般のご家庭でミジンコやゾウリムシを培養・維持することは、かなりハードルが高いと思いますので、まめな換水+生クロレラという育て方も有効ではないかと思います。
大切なことは、メダカに与える生クロレラは微量を心がけることです。
実際に、生クロレラを飼育水に混ぜると、稚魚が何かを食べ始めている様子はすぐに確認できます。
それをしっかり確認できると安心できるのではないでしょうか?

こちらは、増やしたミジンコを集めている様子です。


参考までに、こちらが私が増やしたゾウリムシの画像です。

生クロレラはグリーンウォーターの代替になり得るか?


最初に、私の検証結果による考察であることをご理解ください。
生クロレラは稚魚のエサになるか⇒効果あり
生クロレラに水質浄化の効果があるか
⇒水質浄化効果はなく、逆に沈殿し水質悪化のリスクがある
生クロレラに酸素を産み出す効果があるか⇒効果は期待できない
以上から、生クロレラはグリーンウォータとは似て非なるもので、グリーンウォーターのように万能選手ではなく、あくまで効果的な液体エサだということを前提に使用する必要があると考えます。
また、加温飼育に生クロレラは相性が悪いようです。
みなさまも、生クロレラの使用は、まめな換水とセットでお考え下さい。
室内でも白容器とLEDライトがあればグリーンウォーターの作成は可能

色々書かせていただきましたが、季節に関わらず室内でもグリーンウォーターは作れます。

効率の良いLED照明があると効率よくグリーンウォーターが生成できます。
最後に
ここまで生クロレラとグリーンウォーターについて書かせていただきましたが、いかがでしたか?
本来は年間を通してグリーンウォーターが入手できると良いのですが、特に冬場の入手性は高いとは言えません。
この記事で生クロレラとグリーンウォーターの違いをご理解いただき、そのうえで生クロレラをご活用いただければと思います。
この記事が役立って、みなさまのメダカライフが広がるととても嬉しういです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。