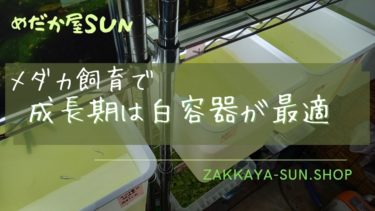改良メダカの魅力の一つに、年中採卵できることによる、品種改良の展開の速さと、チャレンジのしやすさがありますよね!

でも、具体的な品種改良って、単純に好きな品種のペアで卵を取るだけでよいのでしょうか?

私も最初の頃は、柄を混ぜても混ぜても綺麗なメダカにならずに悩んでいました。
実は、品種改良の基本は、学生の頃に生物の授業で習った、顕性遺伝(旧・優性遺伝)とか潜性遺伝(旧・劣勢遺伝)などの要素が複雑に絡みあうんです。
今回は、生物の授業を思い出しながら、メダカの改良に欠かせないメンデルの法則を復習していきたいと思います。
メンデルの法則は、 1865年にグレゴール・ヨハン・メンデルによって確立された、分離の法則、独立の法則、優性の法則の3つからなる遺伝学の法則です。
ヒレ長メダカと、そうでないメダカを掛け合わせても、すぐには子供がヒレ長メダカにならない理由が、この法則によって説明されています。
メンデルの法則の詳細は、専門書などでご確認いただくことをおすすめしますが、まずはこの記事で概略をご確認ください。
※ヒレ長メダカを例示しましたが「リアルロングフィン」の形質(見た目の特徴)は顕性(旧・優性)の遺伝情報のようで、子供の代でも受け継がれることがあるそうです。
その意味で、他のヒレ長の遺伝情報と「リアルロングフィン」の遺伝情報は区別が必要です。

メダカの品種改良に欠かせないメンデルの法則とは

私の手書きイラストで恐縮です。

具体的に以下の図のように、遺伝情報が継承されていきます。


メンデルの法則 F1世代の特徴
F1世代とは、品種改良をする際に、最初に交配した親から見て「子供」にあたる世代を指す用語です。

手書きのイラストの「F1」と記載している列がF1世代のイメージです。

イラストの通りですが、F1世代は顕性(旧・優性)の法則により、どちらか一方の親の形質を有した子供が産まれます。

つまり法則的に子供の世代では、最初にペアにした親同士が混ざった見た目にはなりません。
※「優性の法則」とは顕性(優勢)の遺伝情報のみが、見た目の形質に現れることを指します。
つまり2種類のメダカを交配しても、その「子供の世代(F1世代)」では、片方の親とそっくりな子供しか産まれません。

好きなメダカにヒレ長メダカを掛け合わせても、直ぐに子供の世代でヒレ長メダカが現れないのはそのためです。
※もともとの固定率が低い品種を交配する場合は、F1世代でも柄がブレるので混乱しないようにご注意ください。
※親の前の世代(おじいちゃんの世代)からヒレ長の遺伝情報を隠して受け継いでいる(潜性)場合があるため、絶対にヒレ長メダカが現れないとは限りません。


メンデルの法則 メダカのF1世代の特殊性と注意点

メダカの特殊性と言えるのが、固定率(親とそっくりな子供が産まれてくる確率)が低いことです。
F1世代では、片方の親にそっくりな子供が産まれてくると書きましたが、そもそも親の世代の固定率が低いと、受け継がれる遺伝の情報にもブレが出ます。
そのためF1世代であっても、産まれてきた子供の色や柄がバラけてしまう事態は頻繁に発生します。
そこで産まれてきた子供たちを(採卵の段階から)厳格に分けていないと、どの子供が改良中のF1世代か曖昧になってしまい、正確なF2世代(孫の世代)を産み出すことができす、改良そのものが台無しになってしまうことがあります。


夜桜メダカのように、たくさんの柄が出るメダカで改良をする時には、他の稚魚が混ざらないように注意しておかないと、区別ができなくなります。
そうなるとF2で「ホントに種親の孫なの!?」ってなり、品種改良が失敗する原因になります。

私がよく失敗するのが、採卵時に他のメダカの卵が手に付着していて、気が付かずに卵が混ざってしまうことです。

慎重にやっていても、気が付くと混ざっているんですよね💦
このミスをすると、柄が似ているメダカでは、全く判別ができなくなり大失敗に終わります。
採卵段階でも油断はできませんね。

メンデルの法則 F2世代の特徴

F2世代は最初に交配した親から見て「孫」の世代を指す用語です。
F2世代では「分離の法則」と「独立の法則」により、初めて2種類のメダカのハーフと呼べる色柄のメダカと、見たこともない色柄の子供が誕生します。

この部分については、冒頭の手書きの図のF2の段をご参照ください。
冒頭の図で「ヒレが短い赤いメダカ」と「ヒレ長の青いメダカ」が種親の特徴が混ざったハーフの子供を表しています。
そして、そのハーフの中でも父の潜性情報(隠れた=表面に見えなかった遺伝情報)+母の潜性情報を受け継いだ子供が、見たこともない色柄の子供として顕在化します。
※独立の法則とは、一定の確率で遺伝情報が独立して子供に受け継がれる法則
※分離の法則とは、顕性(旧・優性)遺伝情報の陰に隠れていた潜性(旧・劣勢)の遺伝情報が、潜性遺伝のみを受け継いだ子供によって顕在化する法則

ちなみにヒレ長の遺伝情報は潜性(劣勢)の情報になるので、F1世代では顕性(優性)の遺伝情報に隠れてしまい見た目に現れません。
F2世代でも、メダカの固定率の低さが仇となり、冒頭の図に例示したような 「ヒレの短い赤いメダカ」と「ヒレが長の青いメダカ」は明確に判別できないことがあります。
また、ヒレ長や体外光などの特徴は、孵化後の育て方でも結果に違いが出るため、いっそう正確な判別が難しくなります。
このあたりをしっかり見極めていかないと、次の固定率アップのための累代が曖昧になってしまい、なかなか固定率が上がらない原因になります。
品種改良の上手さ=選別眼の卓越と言われるのは、このような側面もあるのかもしれません。

育て方による結果の違いについては、以下の記事をご参照ください。

メンデルの法則 固定率アップのための累代とは
固定率を上げるためには、F2世代で理想のメダカを選び出し、その個体を親として世代を重ねる(累代)を行う必要があります。

累代とは、理想の形質(見た目の特徴)をもった種親を選んで交配を繰り返すことです。

交配を繰り返して、不要な遺伝情報を排除することで、望む遺伝情報だけが残った固定率の高いメダカを作ることができます。

先人の苦心による累代の結果「幹之メダカ」や「楊貴妃メダカ」など、多くの品種で固定率が向上し、殆ど親と見分けがつかない子供が産まれるようになりました。


逆に「三色メダカ」など、固定率の低さが魅力になっている品種もあります。

そして固定率が低い中でも、綺麗な柄の誕生率を高める工夫が継続されています。
最後に
掛け合わせや累代で、より美しいメダカを作出する際に、メダカの固定率の低さは、メリットにもデメリットにもなります。
また、最高クラスのブリーダーさんになると、メダカの見た目の特徴だけでなく、体形や血筋の健康面(病気に対する強さ)にもこだわって累代をされているそうです。
そこまでこだわった累代をすることは難しいと思いますが、これを機会にメダカの品種改良にチャレンジされてみてはいかがでしょうか?
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


みなさま、品種改良のために卵をたくさん採りましょう!

たくさん産まれたた卵をしっかり育てるために、以下の記事をご参照ください。