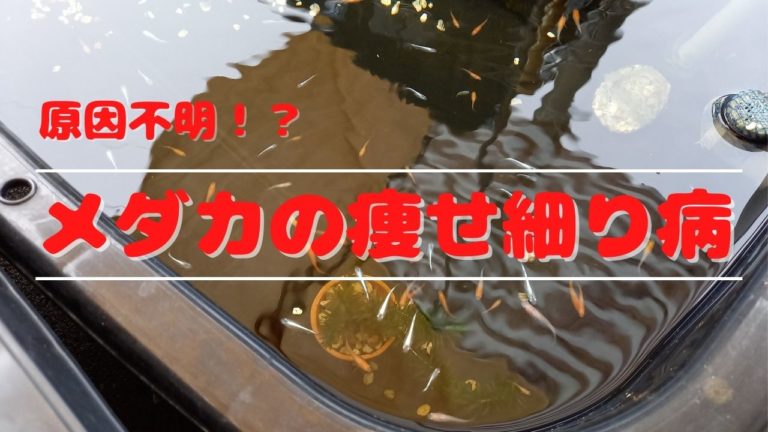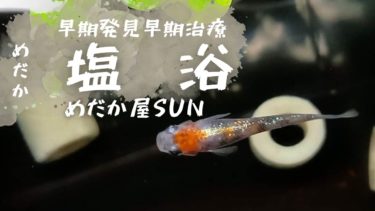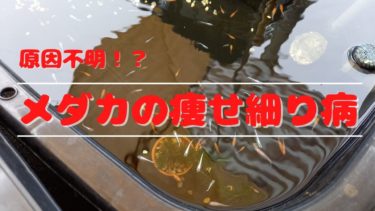みなさまは、メダカを観察していて、ヒョロヒョロと痩せたメダカを見つけてビックリした経験がありませんか?

私が、はじめてマッチ棒みたいに痩せたメダカを見つけた時には、何が起こったのかわからず呆然としてしまいました。

数日前まで、ふっくら元気にしていたメダカが、気が付くとマッチ棒みたいに痩せてしまった。

なんとも言えず不安で、とても悲しい気持ちになりますよね?

今回は、メダカが突然痩せてしまう「痩せ細り病」について、対応方法などをご説明させていただきます。
メダカを観察していると、しっかりと餌を与えているはずなのに、マッチ棒の様にガリガリに痩せて、フラフラと泳ぐ個体を見つけて、驚くことはありませんか?
つい先週までは、あんなに元気に泳いでいたメダカが、なぜこんなにも痩せてしまったのでしょうか?
見かけると、悲しくてやり切れない思いになるのは、私だけではないと思います。
もし、水槽内で急激にやせたメダカを見つけたら、それはメダカの「痩せ細り病」が原因かもしれません。

残念ながら「痩せ細り病」について、明確な原因も治療法も、確実な答えは分かっていないようです。
色々調べた結果や私の経験を踏まえて、やせ細り病の原因はカラムナリス感染症の疑いや、古い餌を食べたことによる内臓系の疾患の可能性が高いようです。
また、私がメダカを飼育し始めたばかりの頃は、「痩せ細り病」は手を尽くしても助けることができない不治の病でした。
それから様々に経験を積む中で、今では早期に発見できれば、なんとか回復させることができるケースも増えてきました。
大切なメダカ達ですから、できるだけ助けてあげたいですよね。
やせ細り病を発見したら、どのような対処と治療が適切なのでしょうか?
今回は、私が実際に治療してきた経験を中心に「痩せ細り病」の原因と治療方法について解説していきます。


キチンと餌を与えているのにメダカが痩せていく「痩せ細り病」とは

ここからは、やせ細り病の原因などに付いて具体的に解説をしていきます。
一匹だけ痩せていく病気「痩せ細り病」の原因と症状について

梅雨時期などで天気が悪い日が続くと、メダカが痩せてフラフラと泳いでいる姿を見掛けることが多くありませんか?
私は「痩せ細り病」を、梅雨や室内の日照不足で見かけることが多いので、紫外線の殺菌不足で病原菌が増加し、感染によりダメージを受けた事が原因の一つではないかなと考えています。
また、日光浴の不足でビタミンDの生成が十分に行われなかったことも原因と考えています。
その他、傷んだ餌を食べてしまい「重度の内臓疾患になったのでは?」というご意見も聞くことがあります。

水流が強くて弱ってしまった説や、単純に餌の取り合いに負けたケースも否定はしません。

ですが、最近まで元気だったメダカが急に痩せてしまうことを考慮すると、その可能性は低いように思います。
隔離して優先的に餌をあげても回復しなかったり、回復しても時間が掛かる事が多いので、何かしら病的なダメージが原因のように感じています。
この病気は、古い餌を食べた可能性と、感染症が原因の可能性が信ぴょう性が高いかもしれません。
・水質悪化と感染症
・日照不足によるビタミンDの生成不足
・消化不良による内臓疾患
・傷んだ餌を食べたことによる内臓疾患
・餌の取り合いに負けた
・強い水流で体力を消耗した など

以下のリンクから、傷んだ餌を残さない安全な給餌方法について、ご確認いただけます。

メダカの「痩せ細り病」を見つけた際の対処法
私なりに色々調べたのですが、前半で書いた通り「痩せ細り病」は、原因も対策もはっきりしていません。
一般的な病気に罹患した場合は、同じ容器の中にいるメダカを全部「メチレンブルー」などの治療薬や「あら塩」で塩浴して治療をします。

でも「痩せ細り病」は他の病気とちょっとやり方が違うんです。

以下に薬浴と塩浴のやり方の記事を載せています。
経験上「痩せ細り病」に薬浴は刺激が強すぎて逆に致命傷になる事が多いので、基本的に痩せ細り病に対しては”薬浴”も”塩浴”も控えています。
治療薬のメチレンブルーとは

メチレンブルーは観賞魚に対して、汎用的に使える殺菌剤です。
※「メチレンブルー」は殺菌、「あら塩」は体力回復に効果があります。
「痩せ細り病」に薬浴や塩浴は危険な可能性
「痩せ細り病」に罹患した疑いがあるメダカを薬浴すると、水質変化に耐えられないのか、死んでしまうことが多い印象があります。
個人的には「痩せ細り病」の治療に薬浴は避ける方が賢明だと思っています。
塩浴も同様で、急激な水質変化は「痩せ細り病」で体力が落ちているメダカにとっては、致命傷になり得ますので、ご注意ください。


メダカをグリーンウォーターの中で栄養保補給させてあげることが大切
私は「痩せ細り病」のメダカを見つけたら、温かい時期なら半日陰(一日の半分日陰の場所)で気温が安定している場所を選んで、グリーンウォーターに優しく水合わせをして引っ越ししています。
そして、しばらくの間はグリーンウォーターに含まれる「植物プランクトン」と、自然発生している「微生物」を餌に、自然回復してくれることを祈ります。
適度に濃いグリーンウォーターは、それ自体が植物プランクトンや微生物の宝庫です。
活用しないのは勿体ないですよね。


このような感じで、元気がない子たちをグリーンウォーターに引っ越して回復させています。


グリーンウォーターは手作りもできますし、購入も可能です。
病気の治療中は市販の粉の餌は避けたほうが安全

私が治療中に市販の粉餌を与えない理由は、
②特に高タンパク質の餌は消化に悪く、内臓疾患が疑われるメダカには負担が大きいから
などです。
基本的に、痩せ細ってしまったメダカは摂食行動をとりません。
そのため症状が悪化した個体だと、市販の粉の餌を与えても、生き餌を与えても無反応であることが多いです。
ですから、治療中は餌の食べ残しが増えがちで、食べ残した餌を放置すれば水質が悪化していきます。

病気に水質悪化・・・そうなると致命的ですよね。
その対策として、自然に口の中に栄養が入るグリーンウォーターは、病中食として最適です。
治療期間の初期は、粉の餌を与えないほうが賢明だと思います。
消化に良い餌を与えることが大切

「痩せ細り病」のメダカは内臓に疾患を抱えている可能性が高いと言われています。

私自身の経験でも、恐らく内臓疾患は原因の一つだと思います。
生き餌の中でミジンコは固い外殻があるので、内臓に疾患があるメダカには負担が大きいかもしれません。
また、ブラインシュリンプは、選別に漏れた卵の殻が、消化不良の面で不安材料になります。

ですから、メダカの栄養面でどうしても生き餌を使いたい場合に、無難なのはゾウリムシだと思います。


経験上ですが、痩せ細って食欲が落ちているメダカは、元気に泳ぎまわるミジンコを追ってくれません。

そう言った理由から、私はグリーンウォーターに含まれる植物プランクトンや自然発生の微生物を中心に活用しています。
先ほども書きましたが、弱ったメダカは餌を食べようとはしません。
ですから、自然にメダカの口に入って半ば強制的に栄養を摂取できる、ゾウリムシやグリーンウォーターが、回復用の餌として一番の選択だと思います。
冬場でグリーンウォーターが手に入いらない時期や、室内飼育のみの方でしたら微量の生クロレラやスピルリナも有効です。
クロレラより、スピルリナの方が細胞膜が壊れやすく消化に良いので、可能でしたらスピルリナをおススメします。

生クロレラも過剰になると水を汚す原因になるので、飼育水がうっすら色付く程度にとどめてください。

スピルリナは消化吸収が良いので、稚魚の餌から成魚用の回復食まで幅広くおススメです。

消化の良さに特化した、回復期用の餌もあります。
粗タンパク質や粗脂肪など、増体させる栄養分を犠牲にして、粗繊維などの消化に良い成分を中心に作られた、消化能力が落ちているメダカに最適な餌です。
念のため一つは持っておくと安心だと思います。
最適な治療法は適度に水温を上げて消化吸収を高めてあげる事
メダカは、水温が高いと消化吸収が良くなり、回復を促進する効果があると言われています。
そこで、屋外では半日陰で寒暖差を抑えながらしっかり温めて、室内では熱帯魚用のヒーターで水温を27℃位に保つと治療効果が高まります。
ただし、加温飼育は水の傷みが早いので、水質悪化にも注意してください。

治療で加温する際には、水温計とヒーターがあると便利で確実です。

メダカは上見(上から見下ろす飼育)が多いので、このような浮かべる水温計があると便利です。

「痩せ細り病」の予防方法について

冒頭でも書きましたが、痩せ細り病の原因は、感染症や内臓疾患の可能性が高いです。
「痩せ細り病」の原因はカラムナリス感染症や内臓疾患の可能性が高いです。
ですから、痩せ細り病の主な予防方法は
1.水質ショックや水温ショックを与えないこと
2.水質維持に努める
3.餌の食べ残しの管理を徹底するの3点になります。

特に梅雨の時期は、雨の降り込みで水質ショックや水温ショックを起こしやすく、植物プランクトンの死滅で水質悪化がしやすい環境にあります。

梅雨などの大雨が降る時期には、波板などで雨対策をしてあげて、もし雨が降り込んだら早目の水換えを実施してください。

様々なショック症状の防止のために、水換え時の注水は、点滴法などを活用して、丁寧な水合わせを心掛けると安心です。
最後に
元気に育っていたメダカが、いきなりガリガリに痩せたらとても悲しいですし、十分に対策できず、ただ死んでいくのを見守ることはもっと辛いことです。
繰り返しになりますが、この病気は明確な原因や治療方法は確立されていません。
ですが、多くの場合、適切な水質管理と水合わせで予防できると思います。
また、発症しても時間をかけて丁寧に給餌を続けることで、回復した事例があることも事実です。
みなさまも「痩せ細り病」のメダカを見つけても諦めずに頑張ってみてください。
この記事が、みなさまのお役に立てると嬉しいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。