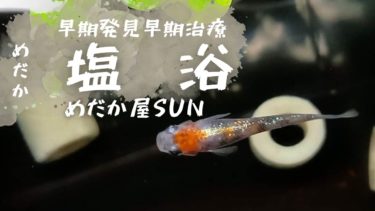みなさま、大切なメダカが病気になってしまったとき、どんな治療方法があるかご存じですか?
具体的には、病気の予防や軽症の時に使う塩浴(塩水浴)と、重症の時に行う薬浴があります。
今日は、メダカを健康に育てるうえで大切な、塩浴と薬浴をまとめてご説明させていただきます。
大切な知識ですので、じっくり読んでいただけると嬉しいです。

みなさまメダカの病気の治療で塩浴ってご存じですか?
なんで淡水魚に塩?って思う方も多いのではないでしょうか?
私も初めて塩浴の記事を見つけた時は、塩水に入れても大丈夫なの?って疑問に思って何度も読み返しました。
実は、お魚の”塩浴”を人間に例えると、風邪の引き初めに温かくして寝るような回復方法なんです。

塩浴は以下のような症状に有効です。
②なんとなく病気っぽい時
③輸送後に餌の食いが良くなくて、しばらく待っても回復の兆しが見られない時など・・・

基本的に、病気の気配がする時や、なんだか元気がない時に使うのが塩浴です。

塩浴は魚を元気にするので、間違って元気な魚を塩浴しても問題はありません。
ただ、健康の為の塩浴も、メダカにとっては水質変化の負担があるので、いざ塩浴する場合も徐々に塩を増やすなど優しい水質変化を心掛けてください。
【STEP1】そもそもメダカの塩浴治療ってなに?

いきなり核心に迫りますが、”塩浴”とはメダカを塩水で泳がせることで、メダカを塩浴すると元気になります。
理由は以下で説明いたします。
つまり、周りの水よりもメダカの体内の塩分濃度の方が高いんです。
そのため、常に浸透圧の影響で周囲の水がメダカの体内に入ろうとする力が働いていて、メダカは水を通さないために粘膜を体の表面に作って水の侵入を防いでいます。
そうすることで、体内の水分と塩分のバランスを維持しているんです。

メダカに限ったことではなく、魚はこの粘膜を作ることにかなりの体力を使っているんです。
体調不良や病気で体力が落ちているときに、体表の粘膜を作ることに体力を奪われると、更にメダカが弱ってしまう原因になります。
そこで、周りの水を塩水にしてしまえば浸透圧を軽減できるよねって言うのが塩浴の意味です。
【STEP2】メダカの塩浴治療のやり方と注意点
塩浴は、塩水の濃度を0.5%(水1Lに対して塩5g)に調節する必要があります。
〇使用する塩について
塩は市販の塩でも問題ありません。
※市販の塩でも大丈夫ですが添加物が悪影響になるので、にがり入りの塩や味付け塩は避けて、いわば成分が塩だけの一番安い塩を選んでください。
ただ、アクア用品の塩浴専用の塩は、大粒のあら塩がジワジワ溶けることで水質ショックの予防に配慮されていたり、専用の計量スプーンが付くなど使いやすい設計になっているのでおすすめです。

塩浴に体力回復の効果があるといっても、いきなり濃い塩水にメダカが晒されると、逆に水質ショックでダメージを受けてしまいます。
対策として、時間を掛けて溶ける大粒のあら塩を使用するか、一般の塩を使用する場合は半日~2日間、ゆっくり時間を掛けて徐々に塩を溶かすようにしてください。
繰り返しですが、いきなり0.5%の塩水にメダカをドボンは絶対にダメですからね。

普通の方だったら「仕事もあるし、2日間もかけて塩分濃度を調整してられないよ」って思いますよね。
ですから、お忙しい方は治療用の塩を使う方が、徐々に溶けてメダカもショックを受けないので安心ですよ。
私も、徐々に塩分調整をしていく時間が捻出できないので、塩浴専用のあら塩を使っています。

私が塩浴をする際は安全第一で必ず塩分濃度を測っています。
これを使うようになってから、水換えや足し水で塩分濃度を間違うことがなくなったので、塩浴の成功率が大きく向上しました。
ですから、個人的には塩分濃度計はおすすめです。
〇メダカの塩浴の治療期間と運用について
塩浴の期間は5~7日が目安です。
でも、実際はメダカの体調を確認しながら調整してあげてください。
塩浴中はろ過バクテリアがいない環境なので、水質の悪化を防ぐために餌を控えた方が良いです。
ただ、回復が遅く塩浴が長期化する場合には、食べ残しがないように注意しながら少量を与えてあげてください。
そして可能な限り一日おきに水を完全に新しくすることをおすすめします。
※塩水の中でろ過バクテリアは死滅します。

容器を二つ準備しておくと、水槽を移動させるだけでいいので水替えが楽です。
〇治療期間のエアレーショの必要性
必ずしもエアレーションが必須ではありませんが、メダカが疲れない程度に優しくエアを噴いてあげると酸欠の防止と、水の攪拌効果が期待できます。
〇メダカの調子が戻ったら
メダカの体調が回復したら、塩水から通常の飼育水に戻します。
いきなりメダカを真水に戻すと、逆に水質ショックでダメージを与えることがあります。
できれば、2日間くらい時間をかけてゆっくり水換えをして徐々に真水に近づけてから、更にしっかり水合わせをして元の水槽に戻してあげると、ダメージを抑えることができます。
〇飼育水槽に直接塩を入れてはダメです

面倒でも塩浴は別の水槽に隔離して実施してください。
面倒だから飼育水槽で塩浴をしたくなるところですが
①塩浴をするとろ過バクテリアが死滅します
②水草も0.5%の塩分には耐えられません
【STEP3】塩浴に適さないケース

塩浴は病状が軽度の時に自然治癒力で回復させる治療法です。
ですから、見てすぐに病気とわかるような状態の場合は、迷わずメチレンブルーなどで薬浴してください。
病状が見てすぐに判るような場合は、手遅れになる前に早急に塩浴ではなく薬浴をしてあげてください。
また、痩せ細り病(目に見えて痩せている場合などは)真水のまま温めてあげる方が治療効果が期待できます。

やせ細り病は塩浴も薬浴もリスクが高いのでおすすめしません。
詳細は下の記事をご確認ください。

メダカが病気に掛かった時、真っ先にしないといけないのが『隔離』、その次にやるのが『薬浴』ですよね。
ただ、メダカの病気といっても色々な種類があって、病気ごとに使う薬が違って、薬効が似ていても色々種類があって、結局全部揃えていないといけないのかよくわからなくて・・・・・・
頭の中がグルグルになりませんか?

今でも、なんの病気?治るの?薬は何がいいの?って、今でも持ってる薬のパッケージを見ながらドタバタやっています。
ですから、飼育を始めたばかりの方がメダカの病気を見つけパニックになっても普通です。
今回は、みなさまがお悩みの病気の症状や薬浴の方法、治療薬のチョイスなどについてまとめてみました。
【STEP4】最初に、メダカの薬浴治療の方法についてご説明します
薬浴の基本は、隔離して治療薬を使った薬浴を数日間行って、病気が治ったら徐々に水合わせをして元の水槽に返すだけの作業です。
メダカの薬浴治療で準備する道具
1.隔離容器(バケツなどでOK)
2.治療薬(病気ごとに異なる)
3.(できれば)エアーポンプ
4.(加温飼育中のメダカは)ヒーター

薬浴中はろ過フィルターを使わないので、酸欠防止と水質悪化の軽減のために、軽くエアレーションをすることが望ましいと思います。
また、体力が落ちているときに水温ショックは避けたいので、加温中のメダカであればヒーターを使用して、飼育水槽と同じくらいの水温に調整してあげた方が安心です。
薬浴の治療日数
薬浴の日数は一般的に1週間程度と言われています。
数日で見た目に病気が落ち着いたように見えることもありますが、完全に治すためにはしっかり薬浴してあげてください。

特に寄生虫の類はしっかり薬浴をしないと再度幼生が取り付いて再発することもあります。
薬浴治療中の餌
薬浴中はろ過が全く効いていません。
その為、水質悪化の原因になる餌やりは避けたほうが無難です。
どうしても薬浴が長くなって餓死が心配な時は、期間中に1回~2回程度、少量の餌をちゃんと食べきったか確認しながら与えて下さい。
薬浴治療中の水換え
薬浴中はろ過ができませんので、できれば2日に1回完全に換水をしてあげてください。
薬の濃度が変わるとメダカが水質ショックを受けるので、換水というより新しく同じ濃度の薬浴容器を作って引っ越す方が安全です。
【STEP5】実際に薬浴治療を行う手順

ここからは、実際に薬浴を行っていく手順をご説明します。
隔離する容器とその水量の確認
適切に薬浴を行うためには、治療薬の用法・用量をシッカリ確認する必要があります。
特に治療薬はメダカに対する負担も大きいので、適切な用量を確認するのはとても大切です。
そのため、最初に隔離する容器を決めて、その水量を確実に把握してください。
隔離容器の水量の確認は、計量カップなどを使うのが一番確実ですが、計量カップがなくてもペットボトルなど容量がハッキリしている容器を使用して、何杯分水が入るかで計算することができます。

薬も限度を超えると毒なので注意が必要です!
治療薬の添加方法
先ほども言いましたが、薬浴用の薬はメダカにとって負担が大きいものです。
ですから、治療薬の添加は可能な限り低濃度から初めて、時間をかけて徐々に適量まで増やして行くことをおすすめします。
薬浴治療期間中

薬浴期間の取扱については、STEP1の記載内容をご確認ください。
薬浴治療が終わったら

薬浴終了後も油断しないでください。
急な真水への移動は、メダカにとって負担が大きいです。
私は、時間をかけて3~4回1/3換水をしながら、徐々に薬剤の濃度を落として行きます。

換水の最後の2回は、これから行く先の水槽の水を使ってあげると、より水質ショックが軽減できると思います。
通常の水合わせだと、最後にメダカが泳いでる水ごと水槽に注ぎますが、少量でも治療薬が飼育水槽に入るのは心配なので、飼育水槽の水に近くなるまで換水を繰り返して、最後は選別網で掬って優しく移動させてあげています。
【STEP6】実際の病気と治療薬の選択について

今回は私の経験でメダカへの感染が多いものをご紹介します。
その他の病気についても別のページで紹介してますので、ご参照ください。
白点病

ヒレになどに白い点が付いていたら、それは白点病の可能性があります。
白点病は、主にメダカの尾びれなどから広がり始め、最終的にエラにまで病気が広がると、メダカが呼吸困難で窒息死してしまう怖い病気です。
白点の大きさは0.5~1.0mm程度で、実は白点虫という寄生虫がその正体です。
白点虫は高水温に弱いです。
ですから、ヒーターで水温を28~30℃に維持しながら薬浴すると更に効果的です。
使用する治療薬は、治療薬中でも最もポピュラーで汎用性があるメチレンブルーで大丈夫です。
尾ぐされ病

急にヒレに切れ目が入ってきたり、徐々にヒレが溶けたように小さくなっていって、その先が赤く充血したよになっているのを見つけたら尾ぐされ病です。
尾ぐされ病は、カラムナリスという常在菌(どんな水の中にも自然に存在する菌)が原因です。
そして、メダカが水質悪化でストレスを受けたり、選別作業中にネットでスレ傷ができると、そこにカラムナリス菌が感染し発病します。
使用する薬剤はグリーンFリキッドです。
そして、病気が重度の場合は単価がグッと上がりますが、グリーンFゴールド顆粒をおススメします。
ミズカビ病

メダカに綿のようなものが付いていたら、ほぼミズカビ病です。
ミズカビは、尾ぐされ病と同じで水質が悪化すると発症します。
ミズカビ菌は真菌類の一種で常在菌なので、水槽の中には常に存在していて、水質が悪化すると増殖してメダカに悪さをします。
ミズカビ病も白点病と同じメチレンブルーで大丈夫です。
その他病気の記事リンク

各病気の詳細は以下の記事をご覧ください。

薬浴はメダカにとって負担が大きいので、早期発見できて軽症のうちは水換えや塩浴で対処する方が安全です。
まとめ
1.元気がない、泳ぎが遅いなどの時は塩浴
2.尾がハッキリとけている、水カビが付いているなど、明確に病気の時には薬浴
3.塩浴も薬浴もいきなり濃い薬液にメダカをいれず、時間をかけて濃くしていくことが大切
4.水換えも同様に濃度の変化に注意する
5.バクテリアが存在しないので水質管理は一層注意する
最後に
せっかく大切に育てているメダカを病気で失うのはとても残念ですよね。
病気でもあっても、早期発見できれば対処できるものがたくさんあります。
日々の観察で、メダカの異常を早めに発見して治療してあげてください。
この記事が皆さまのお役に立てると嬉しいです。