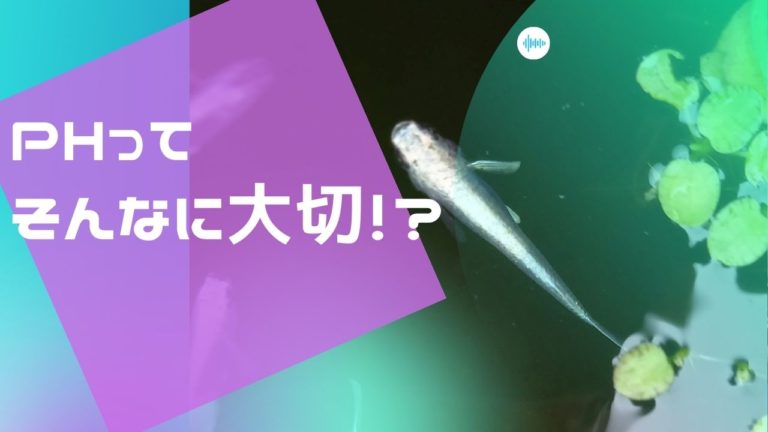みなさま、メダカが好きな「ph」ってご存じですか?

「ph」とは学生時代に理科で習った、酸性とかアルカリ性とかってやつです!

水質を表す代表的な指標の一つとして「ph」や「硬度」などがあります。

先に答えを言うと、メダカは弱酸性から弱アルカリ性(ph6.5~8.0)の軟水(ミネラル分が少ない水=硬度が低い)を好むと言われています。

メダカの飼育に「ph」って、そんなに重要ことなんでしょうか?

今回は「ph」を中心に、メダカの好きな水質と、その重要性について解説させていただきたいと思います。
みなさまは、メダカが好きな水質(ph)をご存じですか?
一般的にメダカが許容できるphは弱酸性から弱アルカリ性(ph6.5~8.0)と言われています。
メダカを飼育するうえで、phってそんなに大切な事なのでしょうか?
気にしないと何か問題があるの?ph対策は?様々な疑問が湧きますよね。
今回は、そんなphを中心に水質と水質維持の大切さについて、ご説明をさせていただきます。
なぜメダカには好みのphがあるのですか?


ph(ぺーはー・ぴーえっち)とは水素イオンの濃度を計測したもので、その値によって酸性とかアルカリ性などと呼称されます。

phは、理科の実験でお馴染みですよね。

でも、なんで弱酸性が好きな魚と、弱アルカリ性が好きな魚がいるんでしょうか?

実はphの好みは、その魚の原産地で決まるんです。
弱酸性が好きな魚の原産地について

著作権などありますから写真を載せれなくて申し訳ありません。
ドキュメンタリー番組でしか見れないような、大きくて泥が舞ってる茶色っぽい河川をイメージしてください。

赤玉土や鹿沼土がそうですが、土って酸性のものが多いんです。
ですから、大きくて泥が舞って茶色に染まった川の水は、弱酸性であることが多く、そう言った川の魚たちは先祖代々弱酸性の水で生きてきたんです。
だから、ネオンテトラをはじめとした熱帯魚の大半は弱酸性の水質を好みます。
弱アルカリ性が好きな魚の原産地について

日本で見かける、岩がゴロゴロの河川をイメージしてください。


こういった川は、石や貝殻から溶け出したミネラル分で、水質が弱アルカリ性になります。
ですから、金魚やメダカなど日本固有の魚は弱アルカリ性の水質を好むんです。
意外ですが、グッピーも弱アルカリ性を好む魚なんですよ。
※メダカは、田んぼの畔や用水路でも生息しているので、土が溶けだした弱酸性の水質にも対応しているのだと思います。
メダカを健康に育てるにはメダカが好きなphで飼育することが大切

魚が好きな「ph」に調整することは、魚が生まれ育った環境に近づけるってことなんです。
ph調整の意味とは、メダカが住み慣れた故郷の環境を作ってあげること

人間も育った風土の環境が心地いいと思います。

メダカのphを調整するとは、住み慣れた故郷の環境に近づけるってことなんです。
私たちも、誰かの勝手な都合で、いきなり砂漠やジャングルへ移住させられたら、なかなか環境に適応できず、病気になって死んでしまいそうですよね?
phを調整することは、慣れた環境で過ごして貰うための、優しさというか思いやりなんです。
phを合わせることは、水質を魚が生まれ育った環境に近づけることで、魚を飼育するうえで大切なことです。
ph調整を上級者がこだわるテクニックと思って軽んじると、魚がストレスから健康を害して死んでしまう原因にもなりかねません。注意が必要です。

メダカに限らず、アクアリウムの生き物を飼育する場合に、ph調整は欠かせなこととお考え下さい!
メダカの水槽のphの測定方法


phはこのような測定器や、検査薬を使うことで確認ができます。
写真のような測定器は、定期的に値を調整しないと、結果が狂っていきます。
私も、今ではph値が狂うリスクがないので、測定器ではなく検査薬を愛用していますが、コスパの面では測定器にメリットがあります。
その他に、リトマス試験紙タイプもありますが、色変化が不鮮明で、phの値が判断しにくいので、あまりおススメしません。
ところでメダカの好きなphって弱酸性?弱アルカリ性?

メダカは、弱酸性から弱アルカリ性(ph6.5~8.0)のまで幅広く対応できる魚と言われてます。

個人的には、ph7.0~8.0の弱アルカリ性の方が、調子が良いように感じています。

最初の説明で行くと、田んぼの用水路などで育ったメダカは、土の成分である弱酸性が好きかもしれませんね。

こればかりはメダカを観察していないと答えはでないので、日々しっかり観察してあげてください。
簡単な調整方法は赤玉土で弱酸性、グリーンウォーターで弱アルカリ性にできる

参考ですが、底石の定番の赤玉土は弱酸性で、グリーンウォーターは弱アルカリ性です。

下の画像は、グリーンウォーターで弱アルカリ性の環境を作っている様子です。


私の経験ですが、飼育水がグリーンウォーターになるだけで、phは10.2(弱アルカリ性)まで上がります。


グリーンウォーターは購入もできますし、ご自宅のお庭で自作だってできます!
私が訪れたことがある天然のメダカの生息地や、グリーンウォーターのphを計測すると7.5~8.0以上の弱アルカリ性でした。
でも、枯葉が溜まった小川や、田んぼの畔などは弱酸性を示します。
ですから、メダカの好きなphは生息地によって幅広いのだと思います。
どうやってphを改善するのですか?phが変化する要因について

先程も少しご説明しましたが、ph調整はとても簡単です!
メダカの飼育水を弱アルカリ性にする方法

最初にご説明した、弱酸性と弱アルカリ性の川の風景を思い出してみてください。
phを調整することは、魚が生まれ育った環境を作り出すこととご説明しました。
まさに、そこに答えがあって、水質を弱酸性に誘導するなら泥(土)を、弱アルカリ性に誘導するなら石(砂利)を、水槽に入れたらいいんです。

ここで疑問に思いませんか?
なぜ、赤玉土に牡蠣殻(かきがら)を混ぜる方がいるのですか?弱酸性の改善方法

右上部にあるのが赤玉土で、右下の白いものが牡蠣殻(かきがら)です。

本来、赤玉土の影響で水質が弱酸性になるところを、牡蠣殻を入れる事で弱アルカリ性に調整しています。


メダカはph変化に耐性があり、徐々にphを変化させると、幅広く順応してくれます。
※ただし、急激にphを変えると、phショックでダメージを受けるので、ご注意ください。
飼育水が、グリーンウォーターになると、phは弱アルカリ性に変化します。
では、グリーンウォーターから、赤玉土の水槽にメダカを移動するとどうなるでしょうか?
ご想像の通り、いきなり移動させると、弱アルカリ性から弱酸性へのphショックを受けます。
また、大量に雨が降り込むと、酸性雨の影響で、水質が弱酸性に急変します。
これも大きなphショックです。
この辺りの理屈がわかっている方は、赤玉土に水質を弱アルカリ性に誘導する牡蠣殻を混ぜて、phを弱アルカリ性に調整しています。
phを維持するために考えるべき事とは
水道から出てくる水は、厳密にはごく弱い弱アルカリ性で、全国平均がph7.3程度と言われています。
※中性がph7.0
そこに、ソイルや砂利を入れることで、水質を弱酸性や弱アルカリ性に誘導するのですが、以下のような理由で、時とともにphは変わって行きます。
飼育水が弱酸性になる原因
①水が汚れた⇒弱酸性へ誘導される
②雨が降りこんだ⇒弱酸性へ誘導される
③グリーンウォーターになる⇒弱アルカリ性へ誘導される
定期的にphを確認することが大切

ここまで書いたように、大袈裟でなくphは刻々と変化します。

そのため、phは定期的にチェックして、調整をしてあげてください。
水槽立ち上げ後にphを再調整する方法について

ここからは、飼育の途中でphを調整する方法についてご説明いたします。
水質を酸性に改善したい場合


ソイル飼育で水質が弱アルカリ性に傾く場合は、水質をアルカリ性に誘導している原因の、石や貝を撤去するのが一番です。
探しても該当がない場合は、市販のph降下剤を使用する方法が簡単です。
ただ、基本的にソイル飼育でphが弱アルカリ性になる事は稀だと思います。

ソイルで飼育するだけでも、phは酸性に変化します。

弱酸性を狙いつつ、水草も飼育されるなら、ソイルの使用がおススメです。

写真に写っているソイルはこちらです。
水質をアルカリ性に改善したい場合


砂利飼育なのに水質が酸性に傾くのを、アルカリ性に改善したい場合は・・・
①水質悪化でphが酸性に傾いている場合が多いので、適切な水換えを行ってください。
②それでも水質が酸性に傾く場合は、水槽内にソイルや赤玉土など酸性の土がないかを確認し、それでも弱酸性のままの場合は、水質をアルカリ性にする牡蠣殻を添加する方法が簡単です。
飼育しているうちに、弱アルカリ性の水が、弱酸性に変化することはよくあることです。

①の水質悪化が原因でphが酸性になった場合は、注意が必要です。

ph変化だけでなく、有害な硝酸塩が増えている可能性があります。

魚にとって有毒な、アンモニアや亜硝酸はこのようなキットで検出できます。



先ほども書きましたが、水中に”牡蠣殻”を添加すると、カルシウムが溶けだして水質が弱アルカリ性に変化します。

上の画像にもありますが、私は牡蠣殻が散らばるのが嫌いなので、このようなお茶用の袋型のフィルターで、小分けにして使っています。
弱アルカリ性に誘導する前に注意すべきアンモニアの害


注意点ですが、弱酸性の水をいきなり弱アルカリ性に誘導すると、アンモニアが重毒化して、急性アンモニア中毒を起こすリスクがあります。
アンモニアの濃度が同じくらいの場合、弱酸性の水と弱アルカリ性の水では、弱アルカリ性の水の方がアンモニアが重毒化します。
そのため、弱酸性の水に牡蠣殻を入れて弱アルカリ性にする前に、必ずアンモニア検査をして、水中にアンモニアが溜まっていないことを確認してから実施するようにしてください。

万が一の、メダカの突然死を避けるため、以下の記事でアンモニアの怖さをご確認ください。
最後に
ここまでphを中心に、水質維持について書いてきましたが、いかがでしたか?
繰り返しになりますが、phを維持することは、魚が本来生活していた環境に飼育水を近づける配慮です。
私も初心者の頃は、上級者レベルの話と軽く考えていましたが、実際にphを調整するようになると、魚が元気になり、ポツポツ死も減りました。
ph管理は、とても大切なことなので、是非気にしてあげてください。
この記事が、みなさまのお役に立てると嬉しいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。