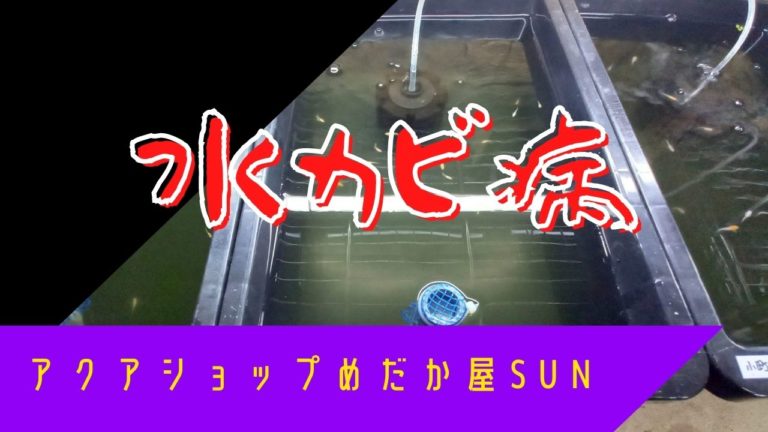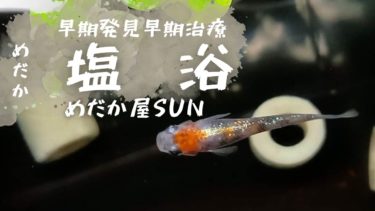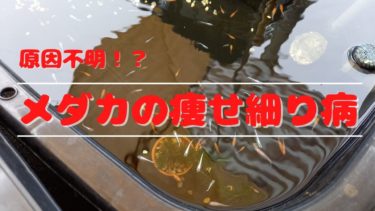メダカを観察している時に、ヒレや体にフワフワっとした綿のような物質が付いていてビックリした経験はありませんか?

私がそれを初めて見つけたときには、何の病気だろうって凄く不安になりました。

もし綿のようなものが付きっぱなしだったら、それは水カビ病という細菌感染です。

急いで対応しなければ、メダカが弱って死んでしまいます。

今回は、とても危険な水カビ病の原因と、対応方法について解説させていただきます。
みなさまは、メダカの表面にフワフワとした綿のようなものが付いているのを見付けてビックリした経験はありませんか?
もし綿のようなものがずーっと付いていたら、それは水カビ病という危険な感染症かもしれません。
水カビ病を放置すると、カビはあっという間にメダカの全身に広がり、最終的にはメダカが衰弱死してしまいます。
どうして、メダカはそのような病気に感染してしまうのでしょうか?
そして、どのように治療したらよいのでしょうか?
今回は、メダカの病気の中でもポピュラーな水カビ病の危険性と治療方法について解説をさせていただきます。

ふわふわと白い綿がつくメダカの水カビ病(綿かぶり病)の症状と特徴は?
水カビ病は、真菌系の水カビ菌による感染症です。
水カビ菌が寄生しやすい場所は外傷や、他の病気でダメージを受けた患部が多く、他の病気と併発が多いのが特徴です。
放置すると水カビは全身に広がり、重症化すると感染した患部の周辺に赤い充血が見られるようになります。

私の経験では、感染の時点で既にメダカが弱っていることが多く、基本的に自然治癒は難しいようです。

ヒレ長タイプのメダカは、選別の際にヒレに擦れ傷を負うことが多く、特に感染しやすいので注意が必要です。
私は、選別時の擦れ傷による水カビ感染が怖いので、ロングフィンの個体は水ごとネットで安全に掬うように心掛けています。
水ごとネットは、水カビ対策でお困りの方におススメのアイテムです。
メダカの水カビ病の原因と予防法について
水カビ病は、サブロレグニア、アクリア、アファノマイヤスなどの水カビ科糸状菌が原因です。
水カビ病の菌は、常に水中に存在する菌(常在菌)ですが、メダカが元気なうちは殆ど感染しません。
感染の主な要因は
・輸送や網による擦れ傷
・水温の低下
水カビ病の予防は、メダカが擦れ傷を作らないための丁寧な管理と、弱らないための水質管理が重要です。
スレ傷対策に効く粘膜保護剤「プロテクトX」の活用法

移動時の擦れ傷ケアに特化した製品が「プロテクトX」です。

メダカの輸送直後のダメージ軽減に、プロテクトXをご活用ください。

水カビ病の治療に効果がある塩浴や薬浴について

水カビ病の治療には、マラカイトグリーンやメチレンブルーを主成分とする「ニューグリーンF」や「ヒコサンZ」などの鑑賞魚用の治療薬が使用されます。
「めだか屋SUN」では体力回復に効果がある「塩浴」に、「グリーンF」の薬浴を併用して治療を行っています。

規定量の治療薬を溶かした溶液の中で、数日メダカを泳がせる治療を「薬浴(やくよく)」と言います。
熱帯魚店で、青い液体の中を魚が泳いでいる風景を見たことがありませんか?それが「薬浴」です。
そして濃度0.5%程度の塩水でメダカを泳がせて、体力を回復させる治療を「塩浴」と言います。
この「薬浴」と「塩浴」の二つが、一般的な病気の治療法になります。
以下に、「薬浴」と「塩浴」の記事を載せていますので詳細は省きますが、病気が軽症の場合は、塩浴で体力を回復させ自己免疫のみでの完治を目指すこともあります。
簡単な薬浴治療の流れと注意点
・原則として薬浴中は餌は与えません。
・突然薬液にメダカをいれると、水質変化のショックでメダカがダメージを受けて逆に弱ってしまう可能性があります。
そのため、水質ショックの対策として、薬の濃度を薄目からジワジワ濃くしていくほうが安心です。
・塩浴も薬浴と同様に、一気に塩分濃度を上げないための工夫が必要です。
食塩などの細かい塩は、直ぐに溶けて一気に塩分濃度が上がるので、ゆっくり溶ける治療用の粗塩を使う方が安心です。
・その他詳細は各製品の説明書でご確認ください。
水カビ病の治療薬の種類と使い方について

メチレンブルーなどの治療薬はけっこう高額ですが、使用量が少ないので長く使えます。
ですが、一回の治療時の使用量は水槽に数滴程度と少量なので、一度買えば使用期限まで十分に使え、コストパフォーマンスはそれほど悪くありません。
メダカの水カビ病などの病気は伝染しないの?

基本的に水カビ病は、細菌感染なので伝染しません。ですが・・・
ただ、一度水カビ病が発生した水槽では、一緒にいたメダカたちも水質悪化などで体力を落としている可能性があり、衰弱から水カビ病にかかるリスクがあります。
大切なことは、発病の原因が擦れ傷なのか、水質悪化による体力低下なのかを、しっかり見極めることです。
原因が水質悪化の場合は、速やかに環境を改善をする必要があります。
メダカの水カビ病の症状は自然治癒しますか?

鯉や金魚などは、稀に自然治癒の事例があるようです。
しかし、メダカは鯉や金魚に比べて体が小さく体力もないので、その点でメダカの自然治癒は難しいと思います。
メダカを救うための確実な対応は、できるだけ速やかに治療してあげることです。
最後に
私の実感として、特に梅雨時期の屋外飼育は「水カビ病」と「尾ぐされ病」が頻繁に発生します。
室内飼育では水換えが不足すると定期的に感染が見られます。
メダカの飼育法は、主に「水換え派」と「ろ過バクテリア活用派(水換えを控える派)」に分かれます。
でも、結局は「水換え派」でも「ろ過バクテリア活用派」でも、切っても切れないのが「尾ぐされ病」と「水カビ病」です。
そして病気の一番の対策は、日々の観察と早期発見だと思います。
大切なメダカ達ですから、優しい目で見守ってあげてください。
この記事が、みなさまのお役に立てると嬉しいです。